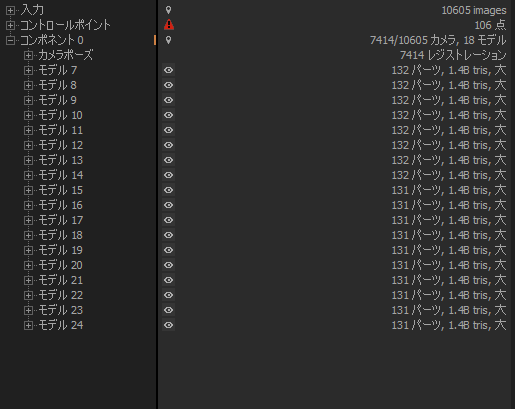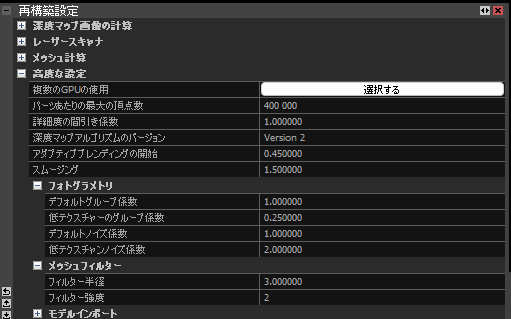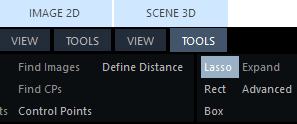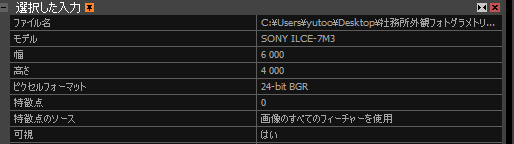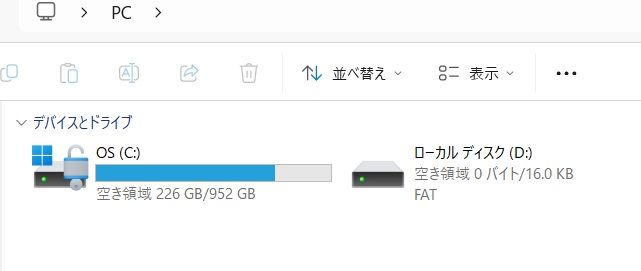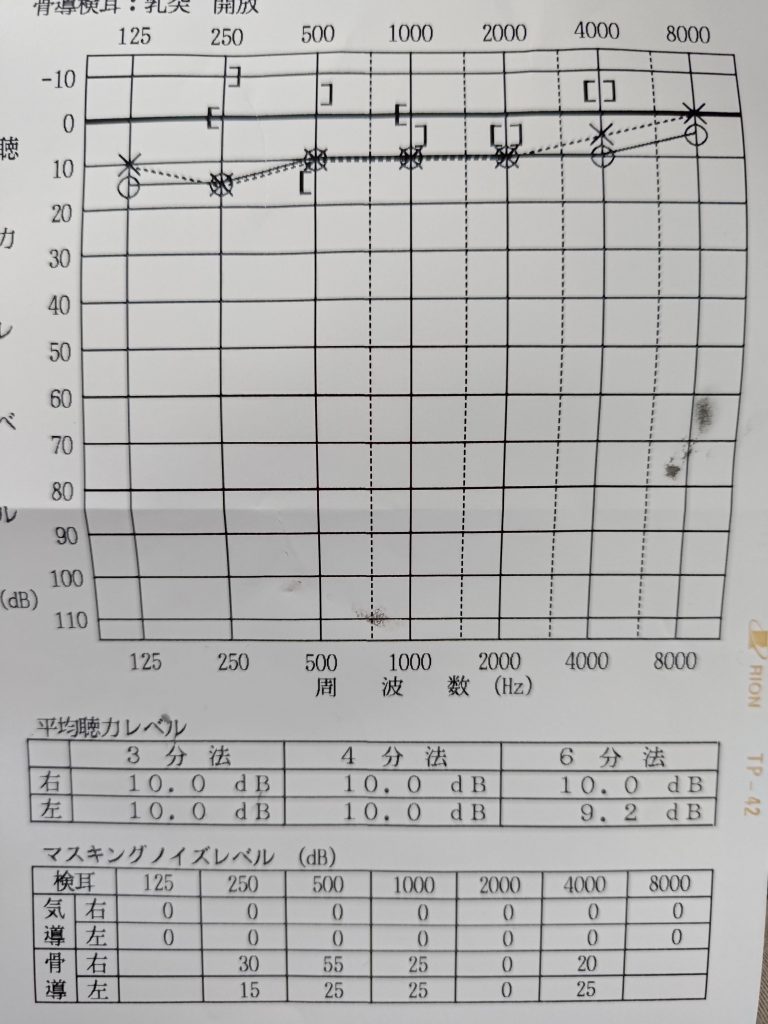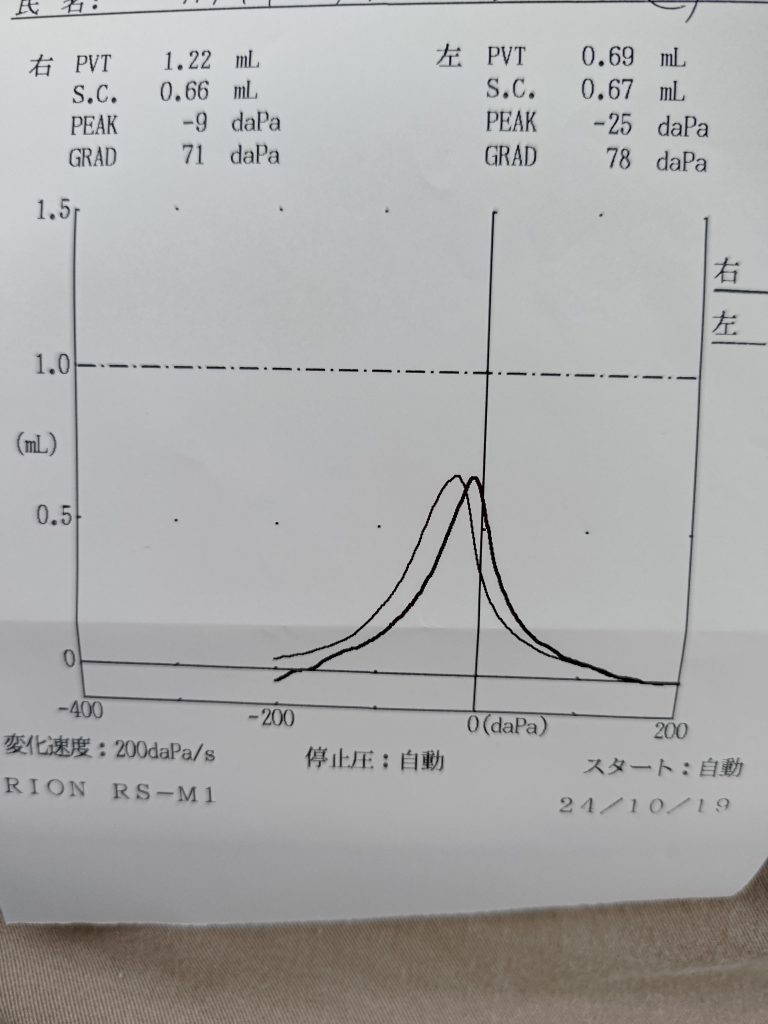QVR Pro Clientでリモートからアクセスする際、躓きやすそうなポイントがありましたので、ご参考までに記しておきます。
導入手順
- インターネットでmyQNAPcloudのアカウントを作成する(フォースメディアさんのページが詳しいです)
- QTS側でmyQNAPcloudを有効化する。
- 設定画面で「myQNAPcloud Link」と「DDNS」を有効化しておく。
- リモート接続したいPC、スマホ等にQVR Pro Clientをインストールする。
- QNAPアカウントでログインし、NAS一覧を取り込む。
- QVR Proが保存されている共有フォルダの閲覧権限のあるユーザーでログインする。
ポイント
☆myQNAPcloudのインストールの際、「myQNAPcloud Link」と「DDNS」の有効化が必要です。この2つは初期設定でオフになっているので注意してください。myQNAPcloud Linkの代わりに、ルーターでポートフォワーディングを設定することで代替できるかもしれませんが、当方の環境ではうまくいきませんでした。素直に有効化した方が楽です。
☆リモート環境からアクセスするユーザーは、録画フォルダへのアクセス権限(Read Onlyで可)が必要です。ローカル環境(LAN内)で閲覧できていても、NASの録画フォルダへのアクセス権限がないとリモートで表示できません。QTS>ControlPanel>ユーザー>共有フォルダ―権限の編集から、「QVRPro・・・」とある全てのフォルダに「RO」または「RW」の権限を付与してください。
☆スマートフォンで入るときは、①左下「NASの追加」→②右下「サインインQNAP ID」からQNAPアカウントでサインイン→③NASが一覧に自動で登録されるので、NASをクリックして共有フォルダの閲覧権限のあるユーザーID/PWを入力。
☆PCで閲覧するときは、QVR Pro Clientのインストール後、「ホストコンピューター」の右側「三」マークから「サインイン QNAP ID」でサインインすると、ホストサーバーにNASが追加されるので、「V」からNASを選択し、ユーザーID/PWを入力してください。ただし、初期表示ではローカルIPで接続する設定になっていますので、ログインの右側の「⇕」マークから、接続方法をmyQNAPcloud LinkかDDNSに変更してください。
※myQNAPcloudで接続方法を「プライベート」にしていると、一度QNAPアカウントでサインインしないと、スマホやPCから接続できません。